カラーインクのおすすめは?メーカーや使い方をご紹介!
◆画材用カラーインクとは?
画材用カラーインクは、主に印刷を前提としたカラー原稿の制作時に使用されてきた着色・描画材料です。
水彩絵具よりも透明度が高く鮮やかな色合いで、他の画材では再現しえない美しい発色が特徴です。特に少女漫画家がカラーイラストの制作に用いるようになったことで一躍広まりました。
その他、カリグラフィーや文字書き用のインクとしても使用されています。また、インクボトル本体の見た目の華やかさから、プレゼント用としても人気のある画材です。

目次
- カラーインクの性質と特徴
- 当ショップで取り扱っているカラーインク
- カラーインクの使い方
- 支持体(紙)について
- 必要な画材・あると便利な道具
- 線や文字を描きたい時は
- 万年筆用インクとカラーインクの違い
- 完成作品を展示したい時は
- カラーインク ~まとめ~
◆カラーインクの性質と特徴
インクの原料には染料と顔料の2種類があり、各々特徴が異なります。多くのカラーインクは染料系で、水に濡らすと溶ける水溶性です。独特な透明感と発色の鮮やかさが魅力ですが、紫外線に弱く日に当たると退色(色褪せ)を起こすという特徴があります。
その為、長期保存を要するものや展示用(観賞用)作品には基本的に不向きの画材とされています。印刷用原稿の着色に適しているのが、染料系カラーインクです。また、退色現象に伴い仕上げた作品はもちろんのこと、インク本体の保管場所も光が当たらないように注意が必要です。
一方顔料系インクは粒子が大きく、染料系インクよりも不透明で落ち着いた発色が特徴です。
インクの伸びが良く、耐光性と耐久性に優れます。透明性・耐水性に関しては各メーカーの仕様、又は色によっても異なります。
ウィンザー&ニュートン ドローイングインク
【耐光性…×/非耐水性/混色…〇/スポイト…×】

乾きが速く、厚く塗ると光沢のある独特の仕上がりになります。ボトルにスポイトが付属していない為、別途購入するとインクを適量取り出しやすくなります。
パッケージがおしゃれで可愛らしく、プレゼント用にも人気な品です。
▼注意点
[1]インクを薄める際は必ず「蒸留水」を使用します。
※水道水を使用した場合、染料と溶液が分離することがあります。
[2]長時間光にさらすと退色(色褪せ)します。使用後は付属の箱へ戻し、冷暗所で保管すること。
ターレンス エコライン
【耐光性…○/非耐水性/混色…〇/スポイト…〇】

透明水彩に近い感覚で使用出来ます。その分発色は穏やかですが、全体的なカラーラインナップにも調和があり、初心者にも比較的扱いやすい仕様となっています。また、水溶性の染料インクでありながら、耐光性もあるのが特徴です。
色数も全60色と豊富でお気に入りの色を見つけられます。「374 ピンクベージュ」や「258 アプリコット」等、他社には無い薄橙系色もラインナップされ、人物を描く際に重宝する色として知られています。
Dr.マーチン
ラディアントインク
【耐光性…×/非耐水性/混色…〇/スポイト…〇】
ボンベイ インディアインク
【耐光性…〇/耐水性/混色…〇/スポイト…〇】

ラディアントインクには発色剤が入っており、非常に鮮やかな色味です。蛍光色に近いくらいに鮮やかな色が多く、画面にビビッドな印象を与えたい場合におすすめです。
インディアインクは顔料ベースのインクのため、耐光性に優れていて、乾くと耐水性になります。そのため、完成した作品を展示したい場合に適しています。
呉竹 ink-cafe
【耐光性… - /非耐水性/混色…〇/スポイト…×】

混色して作ったインクは、ガラスペンや筆などで使えるほか、「からっぽペン」を使ってオリジナルのペンを作ることもできます。「アール・ヌーヴォー」をイメージした色のインクも登場しました。
インクの色を淡くする「うすめの素」、インクをくすみカラーにできる「くすめの素」、インクをかわいいパステルカラーにできて白いインクとしても使える「ミルキーの素」があり、いろいろな表情のインクを作ることができます。
(※ミルキーの素は「からっぽペン」で使用することができません)
アクリルインク
【耐光性…〇/耐水性/混色…〇/スポイト…×】

また、元はアクリル絵具である為、乾くと耐水性になります。エアブラシやカリグラフィーにもおすすめで、幅広く活用できます。
◆カラーインクの使い方
カラーインクで着彩を始めるにあたり、重要であるポイントを下記に解説致します。
インクの取り出し方
カラーインクの瓶底には粒子が沈殿(分離)していることがある為、まずは瓶本体をよく振るところから始めます。
その後スポイトでインクをパレット(溶き皿)へ数適取り出し、水と混ぜ合わせます。基本的にインクの量はわずかで良く、水をたっぷりと使って濃度を調整していきます。
また、水をパレットへ出す際もスポイトを使うことにより、インクとの比率や混色の感覚を掴みやすくなります。
色の調整について
カラーインクはいわば「色を凝縮した液体」です。原液のまま使うことも出来ますが、予め水で薄めてから描くのが基本となります。
カラーインクの扱いが難しいとされる理由の一つは、この「水分量の調節」にあります。幅広い色合いを使いこなすにはある程度の経験が必要です。特に混色時は少しでも配分量が異なると別の色になってしまう為、再現することが難しい場合があります。
広い面積を塗る際は予めインクを多めに作っておくと良いでしょう。また、色を薄めるにあたりホワイトの混色は通常行いません。ホワイトを使用するとカラーインク特有の透明感が失われ、色が濁った印象になってしまいます。
本番前には必ず試し塗り(実験)を!
カラーインクはボトルに入った状態の色、紙に塗った時の色、乾かした後の色、全ての印象が異なります。
その為仕上がったものが「当初イメージした色と違う…」といった状況に陥りやすい画材です。着彩する前は本番用と同じ紙へ試し塗りをし、乾かした上でインクが最終的にどのように定着するか確認するように心がけましょう。
特に混色時は組み合わせによって綺麗に発色しないこともある為、試し塗りは大変重要な工程です。また、予めカラーサンプルを作成しておくのもおすすめです。
各インクの発色を把握することで、よりイメージが掴みやすくなります。
着彩時のポイント
パレット上で濃度調整をしたインクを筆に取り、「馴染ませてぼかしながら塗り進める」のがカラーインクの基本的な塗り方です。
その為、着彩用とは別にぼかし用の筆(水筆)を用意しておくと効率良く塗ることが出来ます。ぼかす際は色の溜まりを動かし、グラデーションの調整なども同時に行っていきます。
基本的には水彩絵具と同じような塗り方ですが、「パレット上でインクの濃度調整をし、紙の上でもさらに調整する必要がある」というのが特徴です。また、水彩やアクリル絵具と比べるとカラーインクは乾くのが速く、ムラになりやすい画材です。
着彩作業はスピードも求められ、乾く前に手早く塗り進める必要があります。
インクの保管方法
使用後のインクは確実に蓋を締め、日光や蛍光灯の当たらない冷暗所で保管します。
保管状態が悪いと退色(色褪せ)に繋がる他、異臭・粘り・カビ等が発生することがあります。また、古いインクを新しいものへ継ぎ足すことも控えて下さい。
開封後の具体的な使用期限は使い方や保管状況により異なります。一度開封したら早めに使い切るように心がけましょう。
▲目次に戻る
◆支持体(紙)について

紙選びは作品の仕上がりを左右する重要なポイントです。
基本的には発色が美しく、表面が毛羽立ちにくい水彩紙の使用がおすすめです。平滑な紙面でフラットに描きたい場合は、ケント紙を使用することもできます。
カラーインクには「ブロックタイプ」と「イラストボード」のタイプの支持体がおすすめです。表面が波打ちしにくく、水張りが不要ですぐに描き始められます。
水彩紙
水彩紙を含め紙には沢山の種類があり、個人により評価や好みが分かれます。目の粗さや吸い込み、発色等を実際に試してみながら自分に合った紙を選ぶようにしましょう。
「キャンソン・ミ・タント」はカラーインク愛用者ご用達の紙で、発色がとても良いので特におすすめです。
KMKケント紙
表面がツルツルした紙がお好みの場合はケント紙の使用もお試しください。但しぼかしを多用する作風には不向きです。
ポストカードパック紙
お手頃価格のポストカードパックは色々な紙を試したい方にお勧めです。
◆必要な画材・あると便利な道具
カラーインクを使用して描く際に必要な画材・道具類をご紹介致します。
水彩筆
カラーインクで着彩する際は主に水彩筆を使用します。
初めの内は着彩用の水彩筆(ナイロン・混毛) 1~2本、ぼかし用の筆(水筆) 1本、面相筆1本があれば充分です。
筆は紙と同様に、個人により扱いやすさが異なる画材です。描き慣れてきた頃に自分のスタイルに合った筆を探してみると良いでしょう。
面相筆
日本画用の面相筆は細かい箇所の塗りや描きこみ時に便利です。
水筆
軸部分に水を入れ、軽く押すことで水を出しながら描ける便利な筆です。ぼかしやグラデーションをつくる際などに重宝します。
とき皿/パレット
インクの調整と手入れがしやすい丸皿やとき皿がおすすめです。
インクボトル
一度作った色の再現が難しいこともあるカラーインクには、混色したインクを保存しておける「空ボトル」があると便利です。
スポイト付きなのでボトル単体で使うことができます。
筆洗器
線画用インク(耐水性)
ターレンス社「エコライン」の【インディアンインク】、Dr.マーチンの「ブラックスター」は耐水性の黒インクです。着彩前の線画用としてお使い頂けます。描く際は文字を書くのにも使える「つけペン」(後述)等を使用します。
ミリペン
耐水性のミリペンも着彩前の線画用にお使い頂けます。「サクラ ピグマ」はカラーバリエーションが豊富で、黒以外で線描きしたい方におすすめです。
◆線や文字を描きたい時は

画材用カラーインクを使って線や文字を描く際は、つけペンやガラスペンを使用します。(※万年筆はペン先に不具合を起こす可能性がある為使用しないでください。)
つけペンは描き慣れるまでに多少の練習が必要になりますが、コツを掴めば筆圧の加減一つで思いのままに線が描けるようになります。初心者の方は硬質で均一な線が描ける、タマペン(カブラペン・サジペン)から始めるのがおすすめです。
ペン先
ペン軸
ガラスペン
◆万年筆用インクとカラーインクの違い
カラーインクは混色できるものが多いのに対し、万年筆用インクは混色が出来ないものが多く、水で薄めることも推奨されていません。
一見画材用カラーインクと似ていますが、仕様が全く異なる為、混合しないようご注意下さい。また、お使いの万年筆とインクのメーカーは統一することが推奨されています。
▲目次に戻る
◆完成作品を展示したい時は

染料系のカラーインクは紫外線に当たると退色(色褪せ)する特徴があります。
その為基本的に作品の展示は不向きとされていますが、対策を施すことである程度退色を防ぐことは可能です。例えば作品を額装する際にUVカットが施されたアクリル板を使用することで、紫外線の影響を抑えることが出来ます。
また、室内のライトに紫外線が発生しないLEDを使用するのも有効です。しかしながら、様々な画材の中でも耐光性・耐熱性が低いのがカラーインクという画材です。メーカーによる差異もありますが、退色しやすい画材であることを念頭に置き、長期展示は控える方が無難です。
尚、作品を保管する際も同様に取扱いには注意が必要です。
※UVカットアクリル板をご注文希望の際には寸法をご指定の上、別途メールでのご依頼となります。
▲目次に戻る
◆カラーインク ~まとめ~

- インクと水を混ぜ、濃度を調整してから着彩する!
- 筆は着彩用とぼかし用で使い分けると効率が良い!
- 本番前に試し塗りをしてインクの定着具合を確かめる!
- 光に当たると退色(色褪せ)する!
- 作品とインクの保管場所に要注意! (展示の際は対策を)
カラーインクはプロ向けの画材として知られていることから、扱いが難しく敷居が高い印象を持たれがちです。
実際インクの調整や定着具合など、要領を掴むまでには多少の時間を要します。ですが、コツさえ掴めば楽しい画材となることは間違いありません。
どの画材にも無い美しい透明感と、鮮やかな色彩を生み出せるのがカラーインクの醍醐味です。是非この機会にカラーインクでしか描けない、発色の良さを生かした作品づくりにチャレンジしてみませんか?

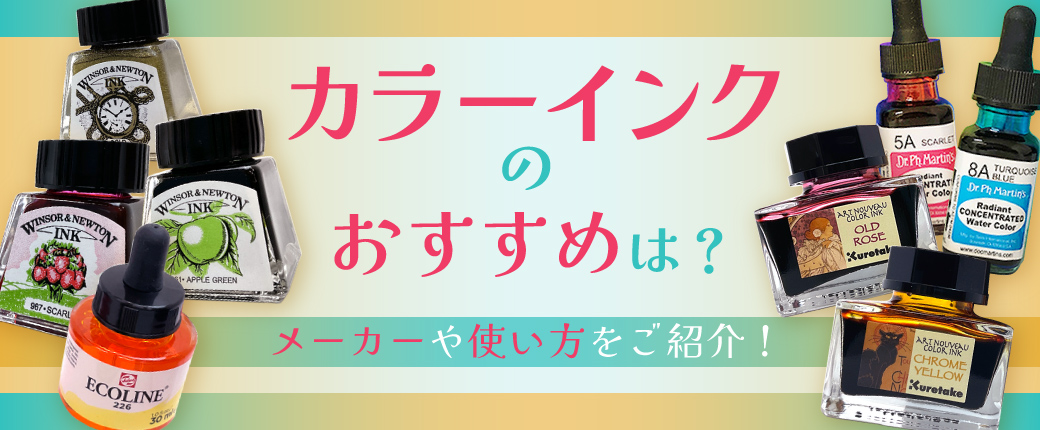
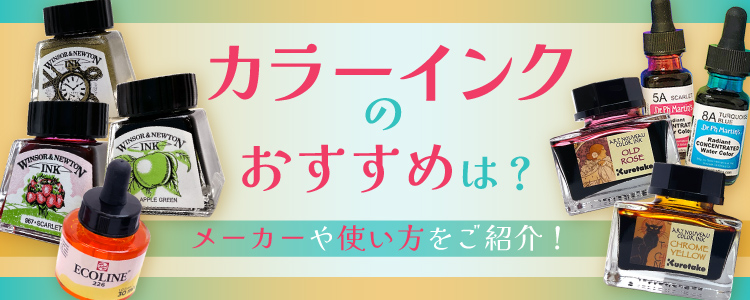












































![マービー フォードローイング[ブラック]](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sekaido-store-image-production/product_images/39282/product/slug_A001095_1.jpg?1565845094)









