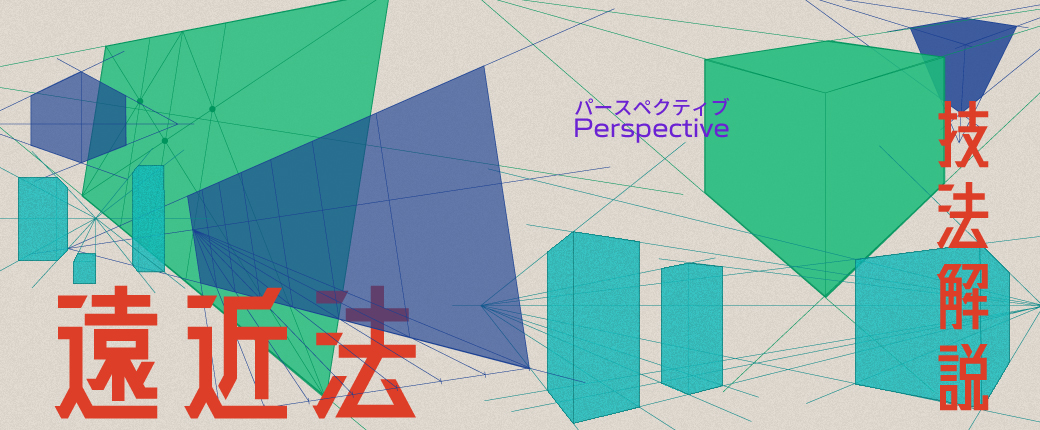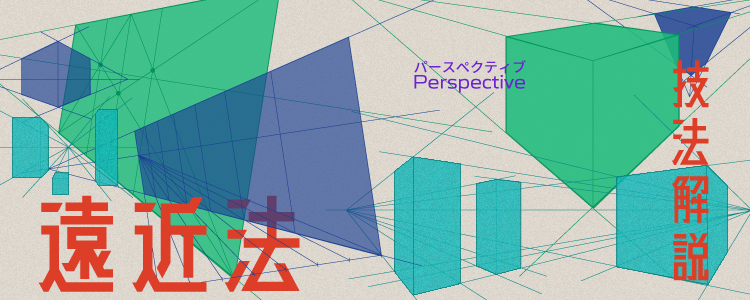遠近法・パースの技法を解説
絵を描くうえで必要となる遠近法の知識。美術学校などではまず始めに遠近法について学びます。遠近法は英語では Perspective と言い、日本では「パース」と略されることが多いです。絵に遠近感があることを「パースが効いている」と表現されます。この記事では遠近感を出すための基本的な技法についてご紹介します。
もくじ
遠近法の種類
・線遠近法
・重畳遠近法
・空気遠近法
・色彩遠近法
・上下遠近法
透視図法
・アイレベル
・一点透視図法
・二点透視図法
・三点透視図法
透視図法を用いた分割
・2等分
・3等分
・さらに多く分割する場合
さいごに
遠近法の種類
絵に奥行をだすための遠近法には様々な方法があります。ここでは代表的な技法を5つご紹介します。
線遠近法

線遠近法とは、消失点(ヴァニシングポイント)を設定し、消失点へ向けて収束する線を基準にして立体空間を表現する技法です。消失点を1つとする「一点透視法」、2つ設定する「二点透視法」、3つ設定する「三点透視法」があります。
重畳遠近法

重畳(ちょうじょう)遠近法とは、距離が遠いものの前に距離が近いものを重ねて描くことによって、もの同士の前後感を表現する技法です。ほかの遠近法に比べるとシンプルでわかりやすい方法です。重なっている箇所は、手前の物をよりくっきりと描き、後ろのものはぼやけて描くとより遠近感が強調されます。
空気遠近法

空気遠近法は、大気によって遠くの物がぼやけて見える効果を利用して遠近感を表現する技法です。山の頂上などから遠くの景色を見ると、距離が遠いほどコントラストや彩度が低下して見えます。静物画や人物画など、実際に大気の影響を受けるようなスケールではないモチーフでも、距離が近い箇所をくっきりと描き、距離が遠い箇所をぼかして描くと遠近感を表現することができます。
色彩遠近法

色彩遠近法は、暖色系の色が前に出てきているように見え、寒色系の色が後ろに引いて見えるという特性を利用した遠近法です。手前のものをより暖色に近い色で描き、奥のものをより寒色に近い色で描くと遠近感が表現できます。
上下遠近法

視点や状況によっても異なりますが、地面に接しているものがモチーフの場合、画面の上に行くほど遠くにあるように見えます。この原理を使用した技法が上下遠近法です。水平線に近づくほどものは遠くにあるように見えるので、水平線よりも上にあるものは、画面の上にあるものがより近くに見えます。
透視図法
人間の視覚的な原理では、近くのものは大きく見え、遠くのものは小さく見えます。その原理を利用した描画技法が透視図法です。
アイレベル

VP=ヴァニシングポイント(消失点)
アイレベルとは視点の高さです。対象を上から見ている場合(フカン)は、アイレベルの線は対象の上のほうにきます。対象の下から見ている場合(アオリ)は、アイレベルの線は対象の下のほうにきます。透視図法で設定する消失点はアイレベルの線上に設定します。
一点透視図法

消失点を1点設定し、その消失点へ向けて収束する線を基準にして立体空間を表現する技法です。対象を正面から見た場合の奥行きを表現するのに適しています。
二点透視図法

消失点を2点設定し、奥行きを表現する技法です。対象を斜めから見た場合の奥行きを表現するのに適しています。
三点透視図法

三点透視図法は、消失点を3点設定することにより、アオリやフカンの視点からの奥行を表現します。一点透視図法や二点透視図法では表現できないようなダイナミックな表現が可能になります。
透視図法を用いた分割
透視図法を用いて、パースが効いている面を分割することができます。その方法を見ていきましょう。
2等分

まず対角線を描きます。対角線同士が交わる点が中心点となるので、その中心線に対して垂直線を描くと2等分できます。
3等分

3等分の場合は、2等分で分割した中心線の上の交点から下辺の両サイドの角へ線を引きます。その線と上辺の角の対角線が交わる交点に垂直線を描くと3等分できます。
さらに多く分割する場合

対象の両端と同じ長さの水平線を図のように描き、その水平線をまず分割します。対象の奥の端の辺とアイレベルの交点から、分割した境目の点へ線を引き、対象の下辺と交わった点から垂直線を引くと、同じ数の分割ができます。
さいごに
絵の中の世界で遠近感を表現する方法はいくつかあります。もしあなたがまだ試していない方法があれば試してみませんか?いつもとは違う遠近法を使うと、普段とは違った雰囲気の絵が描けますよ!